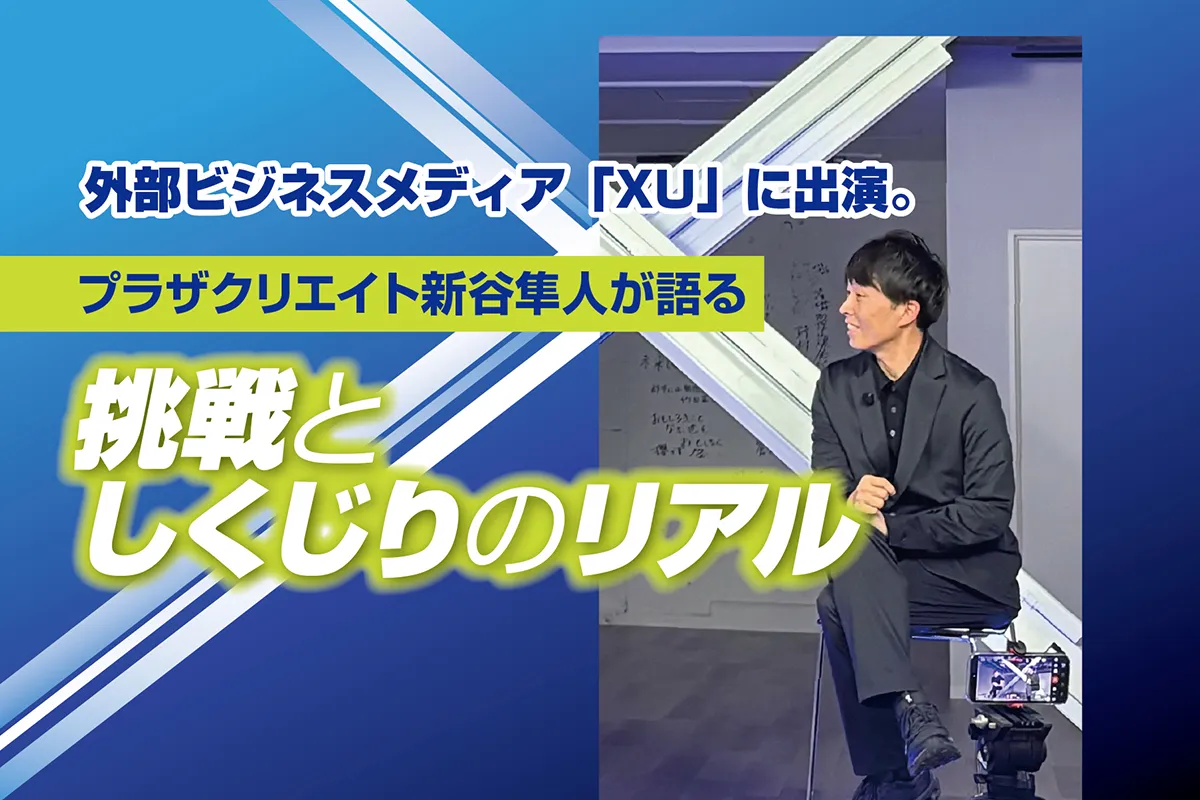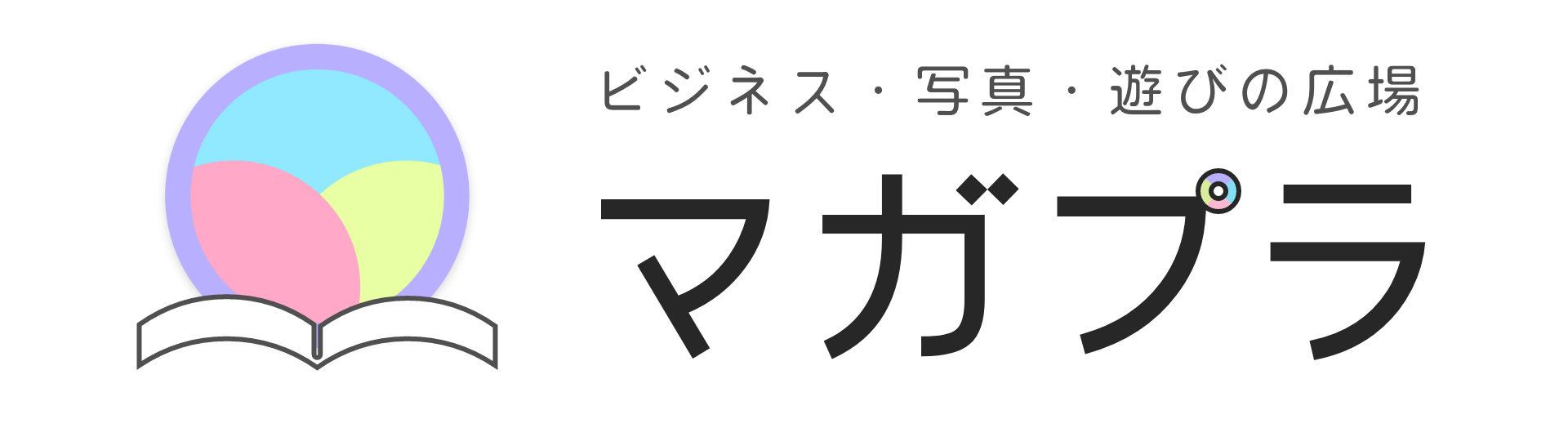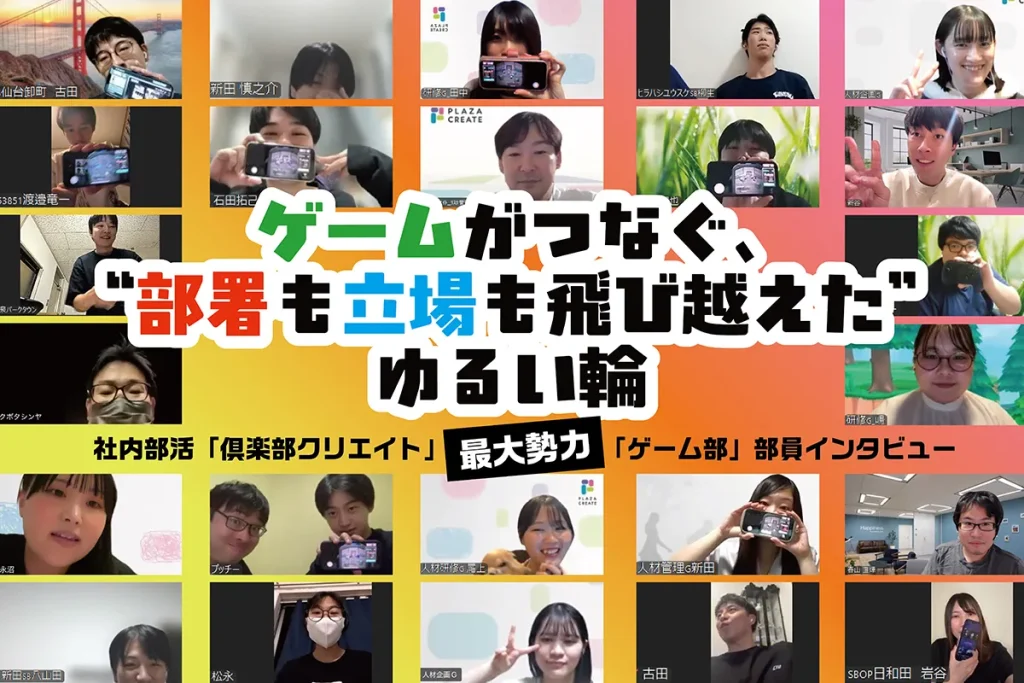落書きした顔を洗わず翌日も登園!? フランスで学んだ「汚れても大丈夫」な子育てと生き方

フランス生活特集・第二弾は、パリ郊外での暮らしが少しずつ日常になってきた頃のお話。子どもの顔に残った落書きを洗わず、そのまま翌日も登園──!?日本では驚かれるような出来事も、フランスでは当たり前。
そこから見えてきた、「汚れても大丈夫」というおおらかな価値観と、日々をもっと自由に楽しむためのヒントをお届けします。
顔に落書きして登園、そして翌朝も……

夏のはじめ。幼稚園に次女をお迎えに行った瞬間、その顔を見てぎょっとした。顔いっぱいに落書きがされている。お昼寝中に誰かにいたずらされたのかと心配して、入口に立っていた先生に問いただすと、「ああ、それはマキアージュよ」と、なんでもないという顔で返された。本人も満面の笑みを浮かべている。
マキアージュとはフェイスペイントのこと。ラメやシール、肌に塗れる絵の具で顔をデコレーションする、幼稚園の人気アクティビティだという。

先生に「ほら、彼女の手も見てみて」と言われて見てみると、ユニコーンとプリンセスのシールが貼られていた。
「それはタトゥーシール。今日はフェット(パーティ)だったから、担任の先生にやってもらったんでしょうね」とのこと。
ちなみに、フランス人は「7月最後の日だから」「今年最後の登園日だから」と、何かと理由をつけてすぐにフェットをする。その日は「校庭でピクニックするから、ついでにフェットしよう」という流れになったそうだ。


家で洗ってみると、落書きはあっさり落ちた。次女は少し残念そうだったが、さすがに翌日までマキアージュ顔で登園するのはまずいだろう。「昨晩、シャワー浴びなかったの?」と思われてしまう……。でも、翌日登園して驚いた。マキアージュのまま来ている子どもたちがたくさんいたのだ。タトゥーシールもそのまま。それでも、子どもだけでなく親もニコニコしている。
フランスでは、「毎日きれいであること」が絶対的な価値ではないようだ。たしかに手洗いもシャワーも、日本ほど徹底されていない。うがいなんて、している子は見たことない。フランス人のママ友にそのことを聞いたら「1日2日シャワー浴びなくても、別に病気にならないし」と涼しい顔をして言った。
時間割のない小学校、絵の具まみれの子どもたち

次女の顔の落書き事件から数日後、今度は小学1年生の長女がやってくれた。
「ただいまー!」
元気よく家の玄関を開けた長女を見た瞬間、思わず「うわっ」と声が出た。Tシャツの袖には緑の絵の具、ジーンズの膝には赤と青が混じった謎のしみ。そして手の甲には、乾いた水色のペンキのような塊がこびりついている。「どうしたの?」と聞くと、「先生が“今日は図工をしよう”って言ったの」と嬉しそうだ。フランスの小学校には、図工専任の先生がいない。授業時間もきっちり決まっておらず、「今日は図工にしよう」と担任の先生が思い立つと、二時間くらい費やされるらしい。もちろん、汚れ防止の配慮もほぼない。
道ばたでおしっこ、ゴミはポイ捨て。「最後にきれいになればOK」

ある日にはこんなことも。公園に着いた直後、次女が泣きそうな顔でこう言った。
「ママー、おしっこ……」
どうして子どもは一番困るタイミングでこう言うのだろう。町中にトイレが少ないフランスでは、こういう時は本当に困る。でも一緒にいたフランス人のママは、動じずこう言った。「そこでしたら?」と。見れば、他にも子どもたちが低木の影で用を足していて、親たちは特に注意もしていない。「我慢する方が、体に悪いわよ」と言われて、次女もそこに参加させてもらった。
さらに驚いたのはマルシェ(市場)でのこと。スイカやチェリーの試食した大人たちが、その場で食べたあとの種や皮を足もとにポイポイと捨てている。あまりの自然さに「えっ、ゴミ箱は?」とあたりを見回すと、そもそも設置されていない。
「大丈夫、あとで掃除の人が全部きれいにするから」と、店員さんがさらりと言った。実際、マルシェ終了後には清掃員が一斉に現れ、道をきれいにしていた。

おしっこも、ゴミも、「その場ではちょっと汚れても、最後にきれいになればOK」——それがこちらのスタンスのようだ。
私は日本で育ってきたから「来た時よりも美しく」「立つ鳥跡を濁さず」という意識が染みついている。トイレは我慢してでも探すものだし、ゴミはゴミ箱に捨てて当然だと思っていた。でも、フランスでは、「今ちょっと汚れること」自体にあまり抵抗がないように思う。「最後にきれいに片づければいい」と、どこか合理的な発想で生活している。
前倒ししても評価されず「最後に間に合えばいい」
この「最後になんとかなればいい」という考え方は、仕事の場でもよく見かける。私はフランスでも育児の傍ら、取材やコンサルティングの仕事をしている。基本的にはリモートだが、あるプロジェクトでは、月に2回程度、クライアントのオフィスにて、フランス人チームとの打ち合わせがある。
ある日、開始時刻ぴったりに会議室に行ったら誰もいない。 「時間、間違えたかな?」と焦って連絡を取ろうとした瞬間、5分遅れでひとり、10分遅れでまたひとり来て、打ち合わせが始まった。そして30分後に、ニコニコしてもうひとりが入ってきた。その後も何度も同じような経験をした。時間通りに会議が始まることは、ほぼない。誰かしらが遅れてくるのが普通で、誰もそのことに突っ込まないし、謝らない。会議が行われて、決めるべきことが決められれば、それでいいのだ。
そのせいか、会議の時間もフレキシブルで、15分で終わることもあれば、90分かかることもある。フランス人と仕事をしていると「前の会議が長引いた。君との打ち合わせの時間を遅らせてもいい?」という連絡をしょっちゅうもらう。「決めるべきことが決まっていないのに、会議を終わらせる」というのも、逆に彼らにとってはありえないのだ。
日本で働いていたころは、会議の始まる前には席についているのが常識だったし、提出物を期限より早く出せば「さすが」と褒められた。ところが、こちらでは早めに仕事を仕上げても、特に評価されるわけではない。むしろ、早めに出してしまうと「あれ、もう提出してたっけ?」と締切日に忘れられていることすら、ある。
大切なのは、「結果として、ちゃんと終わったかどうか」。プロセスやスピードではなく、最終的に帳尻が合っていれば問題ないという文化。だから途中のミスや遅れに対しては、日本より寛容だ。ミスを攻めるより、「どうやって立て直すか」に意識が向いている。最初のうちは、「それでいいの?」と驚き、戸惑った。日本では、“前倒し”や“きっちり”に価値を置くあまり、常に気を張っていたから。「なるはや」という言葉はいつも使われていて、早く終わらせて、また別の仕事を詰め込んでいた。
でも、今では「きっちり・なるはや・完璧」から少しずつ解放されつつある。「今はまだ終わってなくても、ちゃんと終わらせればいい」——そんな彼らと働いていると、肩の力が抜けていく(早く終わらせても、忘れられるだけだし)。

もちろん、こうしたおおらかさにはマイナスの側面もある。街全体が不衛生だから、ゴミ捨て場の近くでは大量のネズミをよく見かける。窓を開けると、必ずハエが入って来てうんざりする。街を歩いていると、ふとした瞬間に、おしっこの匂いが漂ってくることも多い。
会議やイベントの開始時間が遅れると「間に合うように、がんばって急いできたのに……」とモヤモヤしてしまう。バスや電車の遅延や運休は当たり前だけど「最終的に、どうにかして目的地に着けるでしょ」というスタンスだから、職員さんも悪びれない。「暮らしやすさ」という点では、圧倒的に日本に軍配が上がるだろう。
でも、「生きやすさ」を考えたとき、私はフランスを選ぶと思う。それは、一度この「最後に何とかなればいい」自由を知ってしまうと、もう昔のようには戻れないから。もし今、肩に力が入っていると感じている人は、ぜひ唱えてみてほしい。
「大丈夫。何とかなる」と。
きっと、パリの風が、あなたを無事、最終目的地まで運んでくれるはずだ。
(おわり)
(この記事の取材・執筆者)
綾部まと
三菱UFJ銀行の法人営業、経済メディア「NewsPicks」を運営するユーザベースのセールス&マーケティングを経て、独立。フリーランスのライター・作家として、インタビュー記事、エッセイやコラムを執筆。フランス・パリ近郊の町に在住。3児の母。趣味はサウナと旅行。
X:https://twitter.com/yel_ranunculus
Instagram:https://www.instagram.com/ayabemato/