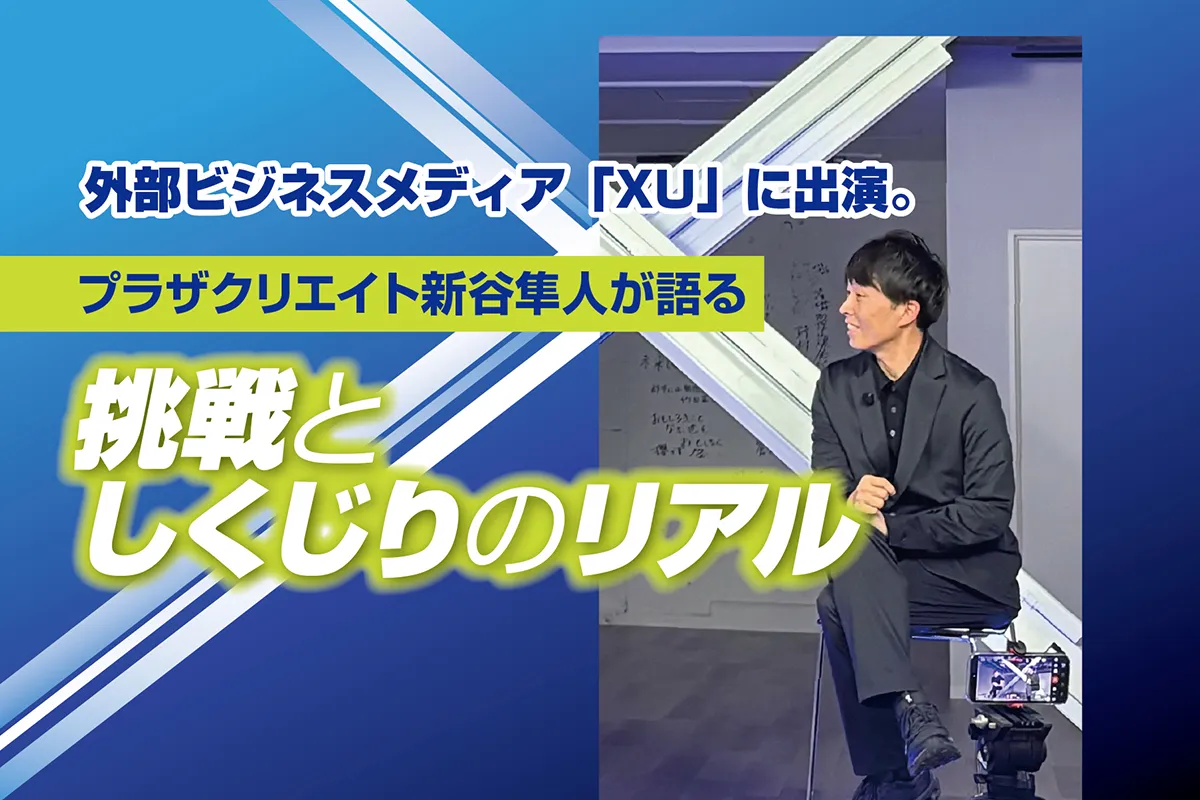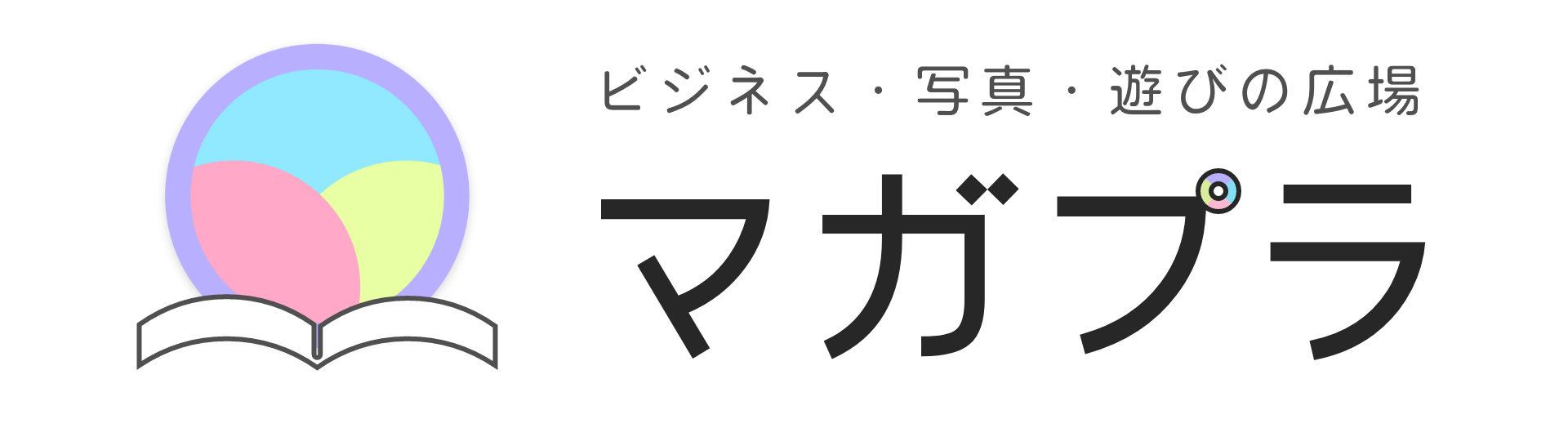プロに教わる花火撮影テクニック!:【第4回】実践編〜体験して分かった花火撮影の難しさと花火の本当の美しさ
.webp)
これまで3回にわたってハナビスト冴木一馬氏から花火撮影の基礎を学んできましたが、今回はいよいよ実践編! 関東で最も早い花火大会として知られる群馬県玉村町の「たまむら花火大会」に足を運び、学んだテクニックを実際に試してみることに。場所選びの失敗から撮影時の苦労、そして意外な発見まで、リアルな花火撮影体験をお届けします。
教えてくれたプロ

打ち上げ会場に向かうところから試練
「群馬の夏は玉村の花火から」ともいわれる、たまむら花火大会。田園地帯で打ち上げられる花火を間近で鑑賞できる迫力満点の花火大会です。
東京から車で移動したものの、前の仕事が午後3時に終わったため、到着は午後5時前。案の定、公共駐車場は満車状態でした。
ま、こんなこともあろうかと、事前に民間の駐車場を予約していたんですけどね!(エッヘン)。ただし、そこは花火の打ち上げ場所から5キロも離れた場所。歩くにはしんどすぎる。そこで前もって自転車を荷台に乗せ、持参してきたのです。

これが結果的に良い判断となりました。というのも、たまむら花火大会は決まった鑑賞場所がなく、打ち上げ会場周辺の好きな場所から観るスタイル。あたり一面に広大な田んぼが広がっており、自転車がなければとても移動は困難だったでしょう。

事前準備では、第1回で冴木氏が教えてくれた通り、運営事務局に問い合わせて「打ち上げ場所の東西方面が全体を見られるのでおすすめ」との情報を入手。プログラムも事前にダウンロードしておきました。やっぱり準備って大事です。
ここでいいの? 土壇場で迷い始める
打ち上げの1時間前、目星をつけた場所に向かうと、大勢の人が椅子を並べて鑑賞の準備をしていました。よし、ここなら大丈夫と三脚を立てたのですが、しばらしてこう思うようになりました──見晴らしは良いものの、距離が2キロ以上あるって大丈夫?
根っからチキンな性格なので、なるべく打ち上げ会場に近づくことに。

しかし、これが完全に裏目に出てしまいました。会場に近づけば近づくほど住宅街となり、建物などの遮蔽物が増えてきます。
打ち上げ時間が刻々と迫る中、後戻りはできません。限界のところで自転車を止め、歩道に三脚を立てましたが、目の前には工場や電柱。完全に詰みました。

あらためて、第1回で冴木氏が強調していた「昼間の下見」の重要性を、身をもって体験することになりました。また、「風上で場所取りをする」という教えも、実際の現場では様々な制約があることを痛感。師匠、申し訳ありません!

撮影本番:教え通りにできないもどかしさ!
いざ打ち上げが始まると、案の定、工場の壁に遮られて花火の全体像が見えません。しかも目の前を頻繁に自動車が通り、ヘッドライトがまぶしくて仕方がない。バルブ撮影のため、長時間露光による白飛びが心配になりました。
ところが、撮影してみると意外とオーケー。工場の影が良い感じで映り込み、車のランプが流れる光の帯のようになって格好良い。これはこれでありなのでは?

最も難しかったのは、シャッターをどれくらい開けておくかの判断。打ち上げた瞬間から花火が開き終わるまで約5秒。その間、教えられた通り開きっぱなしにしたのですが、単発だと明らかに光量が足りません。第1回で学んだND4フィルターで遮光していたからです。NDフィルターを外すという選択肢もありましたが、そこまで瞬時に対処する余裕はありませんでした。


連続花火(スターマイン)では、逆にどこまでシャッターを開けておくかが悩ましい問題となりました。中には1分近く続く花火もあり、露出オーバーで白飛びするのではと不安になりながらの撮影。しかし意外にも、30秒以上開けても白飛びすることはありませんでした。ただし、花火が重なりすぎて雑多なイメージとなり、第2回で冴木氏が語っていた「花火そのものの個性」がなくなってしまいました。

第2回で学んだ「複数発撮影では絞りを調整する」というテクニックも、実際の現場ではテンパってしまって、頭から飛んでいました。よほどカメラの操作になれていないと、教え通りにはできないと痛感。
とりあえず引き気味にして、上がった花火はすべて撮影。途中で場所をさらに近くに移し、別の角度からも撮影を試みました。
無我夢中でシャッターを切るうちに、あっという間に打ち上げ予定の1時間が終了。


花火は「光の線」が織りなす芸術
撮影した写真を確認してみると、使えそうなのは数枚程度。どれもプロの足元にも及びませんが、新しい発見がありました。
それは、花火とは「光の線」が織りなす芸術だということ。破裂した火球の中央から、全方向に光の線が拡散している様子が写真にはバッチリ記録されていました。
肉眼では見たことのない花火の姿。刹那の奇跡を切り取ったといっても大袈裟ではありません。花火の本当の美しさ、そしてこんな写真が撮れる花火撮影の奥深さを知りました。


この体験を冴木氏に報告したところ、以下のようなアドバイスをいただきました。
花火は大きさによって上がる高さが異なるので、一番高いものに合わせて撮影してトリミングするといいでしょう。あとは経験です。アマチュアのインスタをご覧になってもわかるように、週に一回は撮影しています。私も2週間空くと勘が鈍って失敗することがあります。でも、初めてでこれだけ撮れたらすごいと思いますよ
師匠、なぐさめの言葉ありがとうございます…!
4回にわたってお届けした花火撮影テクニック。理論を学ぶことも大切ですが、実際に現場で撮影してみることで見えてくるものがたくさんありました。
失敗も含めて、すべてが貴重な経験。
ぜひ皆さんも花火撮影にチャレンジしてみてください!
(おわり)
【2025年7月号 プロに教わる花火撮影テクニック!シリーズ】
第1回
第2回
第3回
第4回
(この特集の取材・執筆者)


いからしひろき
プロライター、日刊ゲンダイなどでこれまで1,000人以上をインタビュー。各種記事ライティング、ビジネス本の編集協力、ライター目線でのPRコンサルティング、プレスリリース添削&作成も行う。2023年6月にライターズオフィス「きいてかく合同会社」を設立。
きいてかく合同会社: https://www.kiitekaku.com/
(企画・編集・デザイン)


大宮光
株式会社プラザクリエイト・マガプラ2代目編集長