プロに教わる花火撮影テクニック!:【第2回】カメラ選びの常識が変わるプロの裏ワザ

前回は花火撮影の基本をお聞きしましたが、今回はさらに踏み込んだ内容に挑戦!
冴木一馬氏が語る、カメラ選びの真実と複数発撮影のテクニック、そして練習に最適な花火大会の選び方まで、プロならではの視点で花火撮影の奥深さを探ります。
教えてくれたプロ

画素数は少ない方がいい!? 花火撮影に最適なカメラ選び
一般的に「高画素数=高画質」と思われがちですが、花火撮影では全く違う考え方が必要だそうです。
「花火撮影には2000万画素くらいがベストです。3000万画素は多すぎて、ダイナミックレンジの幅が狭くなってしまいます」
ダイナミックレンジとは、カメラが同時に記録できる明暗の幅のこと。この幅が広いほど、明るい部分から暗い部分まで豊かな階調(グラデーション)を表現できます。
画素数が多いと、一つ一つの画素(ピクセル)が小さくなり、光を受け取る面積が減ってしまいます。その結果、ダイナミックレンジが狭くなって、繊細な光の表現ができなくなるのです。
冴木氏によると、カメラメーカーの機材担当者からも「1800万画素くらいがベスト」というアドバイスを受けたそうです。
なお、花火撮影に最適なのはAPS-Cセンサーのカメラだそう。APS-Cとは、センサーサイズの規格の一つ。フルサイズセンサー(35mmフィルムと同じサイズ)より小さなセンサーで、多くの一眼レフカメラに採用されています。
「フルサイズよりもAPS-Cの方が被写界深度が深いので、花火撮影には向いています」
被写界深度とは、ピントが合って見える範囲の前後の幅のこと。被写界深度が深いと、手前から奥まで広い範囲にピントが合います。
「尺玉は直径300メートルの球体なので、手前と奥で300メートルの差があります。被写界深度を深く取らないとピントがずれてしまうんです」
一般的にプロ用とされるフルサイズカメラより、エントリーモデルに多いAPS-Cカメラの方が花火撮影に適しているというのは、意外ですね!
花火撮影用カメラ選びのPOINT
- 画素数は2000万画素くらいがベスト
- エントリーモデルに多いAPS-Cカメラが最適
花火の色と光の特性を理解する
色とりどりの花火をより美しく撮る場合は、基本の7色を知ることが肝だといいます。花火は4原色(青、赤、黄、緑)+3色(紫、金、銀)の計7色が基本ということを前回教えてもらいました。
ただし、同じ色でも花火師によって微妙に違いがあるそう。
「同じ青でも、A社は地中海ブルー、B社は濃紺のジャパンブルーといった具合に、火薬の配合率によって色が違うんです。撮り続けていると、この花火師の青はこうだということがわかってきます」
色も大事ですが、「トーン」も重要だと冴木氏は言います。
「花火は光の線なので、実は立体感や質感が出にくいんです。大切なのはトーンです」
トーンとは、明暗の変化のこと。花火の光の線一つ一つをよく見ると、同じ赤でも明るい赤から暗い赤へと美しいグラデーションを描いていることが分かります。
「光の線一つ一つの色のトーンをきれいに出すためには、ダイナミックレンジの幅が重要。だから画素数は少ない方がいいんです」
色と光の特性
- 同じ青でも火薬の配合率によって色が異なることを理解する
- 花火はグラデーションを持つ光の線であり、1本1本を際立たせるのに重要なのはダイナミックレンジの幅
複数発撮影の高度なテクニック
1発でなく、複数の花火が同時に開くことがありますよね。その瞬間を1枚の写真に収めるには、「重ね撮り」のテクニックが必要です。
「1発だけ撮るなら絞りF13ですが、2発、3発と重ねたい場合は、光の線が重なった部分の露出が倍になるので、その分絞りを絞る必要があります」
露出とは、センサーに当たる光の量のこと。複数の花火が重なると、その部分だけ光量が増えて白飛びしやすくなるのです。
「横に並んで2発だったらF13でもいいですが、重なる位置に2発だったら、重なった部分は露出が2倍になります。5発ぐらい重ねたいときは、最初からF22にして、3発単位で狙ってシャッターを切っていく感じですね。自分で何発重ねたいかを最初に決めて、それに応じて絞りを調整するのがコツです」
このテクニックをマスターすると、華やかで迫力のある花火写真が撮影できますよ。
POINT
- 花火の重なりをあらかじめ想定し、絞りを調整する
練習に最適な花火大会の選び方
近年、花火大会の開催方法に大きな変化が起きています。
「昔は夏に集中していましたが、最近は春や秋の分散開催が増えています」
この流れの先駆けとなったのが熱海の花火大会です。
「熱海は四季を通じて花火大会をやっていて、月曜や金曜などの平日にも開催されています。平日にやると警備費がかからず、閑散期にお客さんが来てくれる。この話を僕がいろんな雑誌で書いたら、各地の温泉地が真似するようになりました」
実は、こうした小規模な分散開催の花火大会の方が、写真撮影には向いているそう。その理由を冴木氏は以下のように説明します。
理由1: 場所取りが楽
「人が少ないので、打ち上げの直前でも三脚が立てられることがあります。集中開催だった頃は混雑して、昼に行かないと三脚が立てられない状態でした」
理由2: 再チャレンジができる
「回数が多いので失敗してもすぐに修正して次に挑戦できます。大きな花火大会で失敗すると次は1年後。でも分散開催なら確実に腕が上がります」
花火は撮れば撮るほど奥が深く、ハマってしまう魅力があるようですね。
第2回では、カメラ選びの常識を覆す話から、実践的な撮影テクニックまで、より深い内容をお聞きしました。次回は、スマートフォンでの撮影方法と手持ち花火の撮り方、そして冴木氏の作品作りへの思いについて伺います。お楽しみに!
【2025年7月号 プロに教わる花火撮影テクニック!シリーズ】
第1回
第2回
第3回
第4回
(この特集の取材・執筆者)

いからしひろき
プロライター、日刊ゲンダイなどでこれまで1,000人以上をインタビュー。各種記事ライティング、ビジネス本の編集協力、ライター目線でのPRコンサルティング、プレスリリース添削&作成も行う。2023年6月にライターズオフィス「きいてかく合同会社」を設立。
きいてかく合同会社: https://www.kiitekaku.com/
(企画・編集・デザイン)

大宮光
株式会社プラザクリエイト・マガプラ2代目編集長





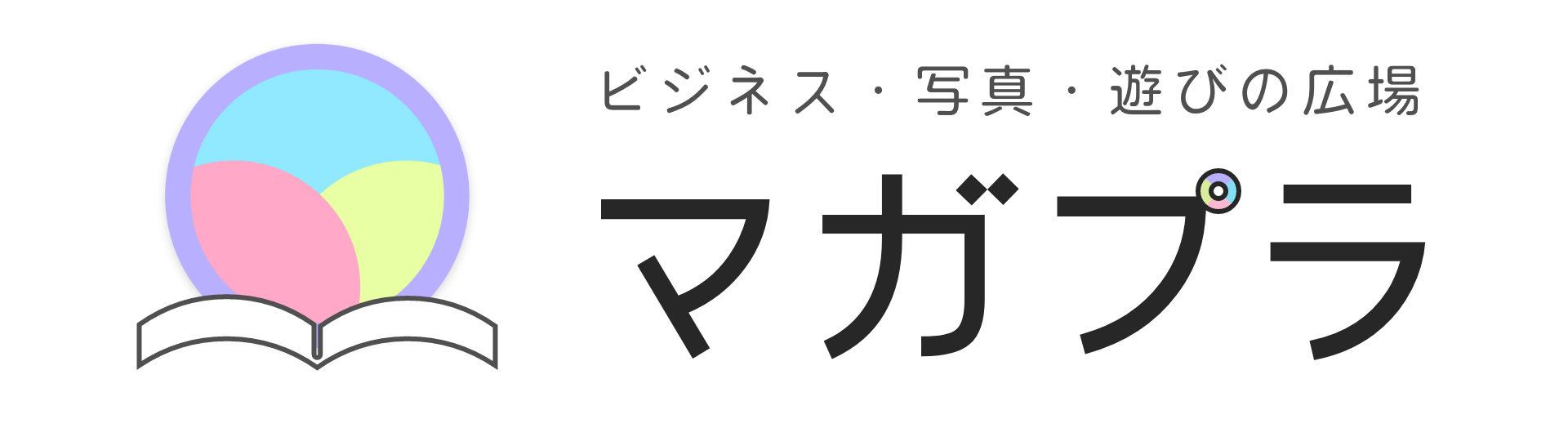



.webp)







