プロに教わる花火撮影テクニック!:【第1回】 場所選びとカメラ設定だけであなたの写真は劇的に変わる

夏といえば花火の季節。近頃は撮った写真をSNSにアップしている人も多いですよね。せっかくなら、誰からも「いいね!」と言われる素敵な花火写真を撮りたい!
そこで、一眼レフカメラは持っているけど全然使いこなせていないライターが、花火写真専門家として30年以上活動する「ハナビスト」冴木一馬氏に弟子入り!
第1回は、花火撮影の成功を左右する「場所選び」と「基本的なカメラ設定」について、プロの技を惜しみなく教えていただきました。
教えてくれたプロ

まずは「昼間の下見」から始めよう!プロの場所選びテクニック
「花火撮影で一番大切なのは、実は撮影テクニックよりも場所選びなんです」と冴木氏は力説。
「まず昼の間に現場へ行って、筒の位置を確認してください」
筒とは、花火を打ち上げるための発射台のこと。ここから花火が空に向かって発射されます。この位置を把握することで、花火がどこに上がるかを予測できるのです。
「主催者のところでプログラムをもらってください。そこに花火の大きさが書いてあります。尺玉なら300メートルの高さまで上がるので、自分の立ち位置から見た角度で、どのレンズを使うかが決まります」
「尺玉」とは、花火玉の大きさを表す単位。一尺玉は直径約30センチの花火玉で、「二尺玉(直径約60cm)」や「三尺玉(直径約90cm)」などもあります。
位置決めで最も重要なのが風向きの確認です。
「必ず風上で場所取りをしてください。風下にいると煙が流れてきて、せっかくの花火が煙で見えなくなってしまいます」
昼に下見をした場合は、スマートフォンの天気予報で、花火大会が行われる日の夜の時間帯の風向きをチェックしておくといいでしょう。
面白いことに、観客席は風下に設定されていることが多いそう。
「観客席の人たちは『今年もよく見えなかったね』とよく言うんですが、反対側から見るとすごくきれいに見えるんです。だから川の土手で花火大会をやっている場合は、反対側の土手に行ってみるといいですよ」
位置取りのための3つのPOINT
- 昼の間に、発射台の位置を確認する
- プログラムで花火の大きさを確認する
- 天気予報で風向きを確認する
カメラ設定の基本:常識を覆すプロの設定方法
さて、そろそろカメラの設定の話に移りましょう。
POINT1: ISO感度
ポイントとなるのがISO感度。これは、カメラが光をどれだけ敏感に感じ取るかを表す数値で、一般的に暗いところでは高いISO感度(高感度)に設定します。
「花火も夜だから高感度で撮る、と思いがちですが、これは大きな間違いです。花火の光は、実はすごく明るいんです。だからISO感度は最低の100に設定してください。50という設定ができるカメラもあります」
POINT2:撮影モード
そして、花火撮影の基本は「バルブ撮影」です。
バルブ撮影とは、シャッターボタンを押している間だけシャッターが開き続ける撮影方法。自分の好きなタイミングでシャッターを開閉できます。
POINT3: ケーブル付きのリモートシャッターの使用
「大事なのは、必ずケーブルレリーズを使うことです」
ケーブルレリーズとは、カメラに接続するケーブル付きのリモートシャッター。これを使うことで、カメラに直接触れることなくシャッターを切れるため、いわゆるブレを防げます。
「ワイヤレスのレリーズもありますが、電波で信号を送るため、どうしてもタイムラグ(時間差)が生じます。リアルタイムでシャッターがキレる、ケーブルの方がおすすめです」
POINT4: シャッターのタイミング
撮影のタイミングについて、冴木氏は明確なルールを教えてくれました。
「筒から火が出た瞬間にシャッターを押し、花火が開き終わったら離してください。花が開く場所を見て押したのでは必ず遅れます。必ず筒を見てください」
花火が筒から発射される際、「曲導(きょくどう)」と呼ばれる光の尾を引いて上昇します。この光の筋も含めて撮影することで、花火の動きと美しさを完全に捉えることができるそうです。
POINT5: 絞り値とフィルター
絞り値の設定も重要です。絞り値(F値)とは、レンズの中にある絞り羽根の開き具合を表す数値。F値が小さいほど絞りが開いて多くの光を取り込み、F値が大きいほど絞りが閉じて光量を制限します。
「フィルム時代はF8を推奨していましたが、デジタルカメラは暗い部分を明るく映す性能が格段に向上しているので、F13くらいがおすすめです」
コツは、NDフィルターで白飛びを防ぐこと。NDフィルターとは、「Neutral Density(中性濃度)フィルター」の略で、レンズに装着して光量を減らすためのフィルターです。サングラスのような役割を果たします。
白飛びとは、明るすぎて画像の一部が真っ白になってしまう現象。一度白飛びすると、後から修正することはできません。 「最初からND4という種類のフィルターをつけておくことをおすすめします。特にオープニングやラストの連続花火(スターマイン)では、最高絞りのF22でも白飛びしてしまうことがあります。ND4は入ってくる光量を2段分減らせるので、F13の絞りでND4を使えば、実質F26相当の効果が得られます」
レンズ選びと構図の基本
「日本の花火は丸いのが特徴です。広角レンズで撮るとせっかくの丸い花火が歪んでしまうので、なるべく50mmの標準レンズで撮ってください。どうしても下がれない場合は広角を使用しますが28mm以上になると周辺も大きく歪むので35mmくらいまでがオススメです」
背景を活かした構図作りもポイントだそうです。
「花火だけでなく、背景の建物や景色も入れて撮ることをおすすめします。そうすることで花火の大きさがわかりますし、その土地らしさも表現できます」
POINT
- 50mmの標準レンズが基本。広角を使用する場合は35mmくらいまで
- 背景を生かした構図を
初心者が陥りがちな失敗とその対策
その1: ピント
気になるピント合わせですが、「花火撮影では、オートフォーカス(AF)ではなく、マニュアルフォーカス(MF)で無限遠に設定するのが基本」とのこと。
無限遠とは、レンズのピントを最も遠い位置に設定すること。花火は非常に遠い場所で爆発するため、無限遠に設定しておけば確実にピントが合います。
「オートフォーカスのままバルブ撮影をすると、ピントが行ったり来たりして不安定になってしまいます」
その2: データの保存形式
データの保存については、RAWデータを推奨。RAWデータとは、カメラが捉えた光の情報をそのまま記録する形式で、J-PEG形式と違い、後からの色調整や明るさ調整に対して非常に柔軟に対応できます。
「RAWデータで撮影すれば、後でパソコンを使って色温度や明るさを細かく調整できます。特にデジタルカメラの利点として、アンダー(暗く写った写真)は後から簡単に明るくできますが、オーバー(明るすぎて白飛びした写真)は元に戻せません」
その3: 色温度設定
後で修正できるとはいえ、事前の色温度設定は重要です。色温度とは、光の色を数値で表したもの。単位はK(ケルビン)で表記されます。数値が低いと赤っぽく、高いと青っぽくなります。
「色温度は4000Kくらいに設定するのがおすすめです。花火は基本4原色(青、赤、黄、緑)+3色(紫、金、銀)の計7色なので、全ての色にぴったりというわけにはいきませんが、4000Kが一番見た目に近い感じになります」
第1回では、花火撮影の基礎となる場所選びとカメラ設定について詳しく解説してもらいました。次回は、より実践的な撮影テクニックと、カメラ選びの意外な真実について冴木氏に教えていただきます。お楽しみに!
【2025年7月号 プロに教わる花火撮影テクニック!シリーズ】
第1回
第2回
第3回
第4回
(この特集の取材・執筆者)

いからしひろき
プロライター、日刊ゲンダイなどでこれまで1,000人以上をインタビュー。各種記事ライティング、ビジネス本の編集協力、ライター目線でのPRコンサルティング、プレスリリース添削&作成も行う。2023年6月にライターズオフィス「きいてかく合同会社」を設立。
きいてかく合同会社: https://www.kiitekaku.com/
(企画・編集・デザイン)

大宮光
株式会社プラザクリエイト・マガプラ2代目編集長





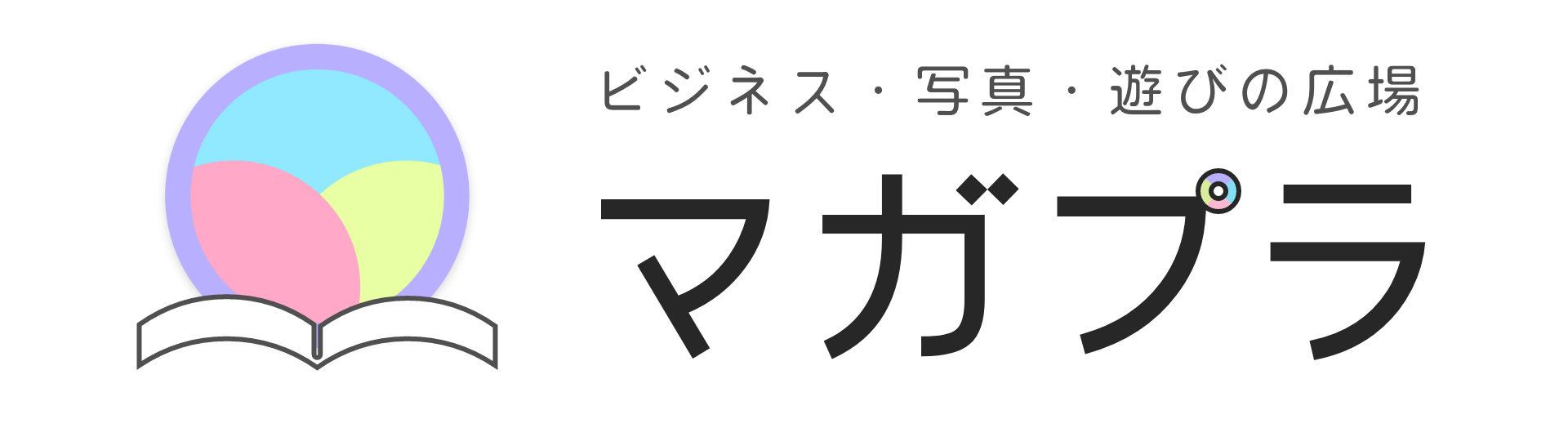



.webp)







